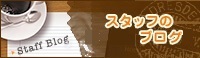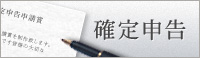役員退職給与が分割支給され、
年度を分け損金として処理することが認められるかが問題となった事案。
所得税、法人税法いずれも納税者が勝訴し、課税庁は控訴せず確定している。
退職所得は、長期にわたる勤務対価が一時期にまとめて後払いされるもので、
個人にとっても、法人にとっても金額的な影響は大きい。特に、個人にとっては、
退職後の生活保障的な所得であること等が考慮されるため、
所得計算には特別な恩典が認められており、恩典を最大限に享受するために、
ルールに基づいたシュミレーションを重ね、取引を慎重に実行する。
分割支給の理由は法人の資金繰りの都合であろうが、
判決から、杓子定規な条文の理解だけでなく、
一般に公正妥当な会計慣行というわれるものの範囲の広さ、
そして判決のポイントとなる認定される事実の形成について
開眼するところがあった。参考までに概要等を紹介する。
事案の概要
・原告会社Xの創業者Aは、H19.8.31に代表取締役を辞任。
以後、非常勤取締役となった。役員報酬は月額87万円から40万円に変更。
・Xは、H19.8.31、Aに対し、退職慰労金の一部として7500万円(第一金員)を支払い、
H19.8期における損金の額に算入して法人税の確定申告をした。
・Xは、H20.8.29、Aに対し、退職慰労金の一部として1億2500万円(第二金員)を支払い、
H20.8期における損金の額に算入して法人税の確定申告をした。
・課税庁は、第二金員は退職給与に該当せず、H20.8期において損金の額に算入することは
できないとして、H20.8期に係る法人税の更正処分、過少申告加算税の賦課決定処分、
源泉所得税の納税告知処分、不納付加算税の賦課決定処分を行った。
通達の定め
・法人税基本通達9-2-28では、役員に対する退職金の算入の時期について、
原則として退職給与の額が具体的に確定した日の属する事業年度とするとしつつ、
例外的に支払った日の属する事業年度において損金算入した場合にはこれを認めている。
・一方、分掌変更の場合の退職給与については、同通達9-2-32の注で、
原則として未払金等に計上した場合の当該未払金等の額は含まれないとしており、
実際に支払ったものに限られる旨定めている。
事実認定
・当時法人が作成した計算書では2億5000万円を分割して3年以内に支給する旨が記載されている
・市役所に対して総額2億5000万円の退職慰労金を支給することを前提に
総額を計算した上で、現実の支給額に応じて按分計算した住民税及び所得税を納付している
判決
・(略)支給年度損金経理は、企業が役員退職給与を分割支給した場合に採用することがある会計処理の一つであり、
多数の税理士等が、同通達但し書きを根拠として支給年度損金経理を紹介しているのであって、
これに依拠して支給年度損金経理を行うという会計処理は、相当期間にわたり、相当数の企業によって
採用されていたものと推認できることをも併せ考えれば、
この損金経理は、役員退職給与を分割支給する場合における会計処理の一つの方法として
確立した会計慣行であるということができる。
監査課 石巻
- Posted by 2016年07月31日 (日) |
 コメント(0)
コメント(0)
この記事へのコメント
 コメント投稿
コメント投稿
※コメントは承認制のため、投稿をしてもすぐには反映されない場合があります。ご了承ください。
※スパム対策の為、お名前・コメントは必ず入力して下さい。
※記事が削除された場合は、投稿したコメントも削除されます。ご了承ください。