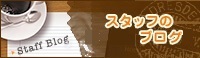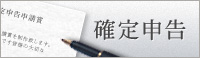アベノミクス効果、とりわけ金融緩和による円安の影響を受け、大企業を中心として業績が上向いている。特に輸出産業では、円安による輸出売上収入の増大、海外子会社の業績を現地通貨から円換算する際の利益増大効果によるところが大きい。これをもって、日本企業の実力が増したと判断することは正しいものとは言えないのではないかと思う。そうは言いながらも、景気は「気」に左右されるため、消費支出の増大による景気回復も見込まれ、この春闘では、各企業の労働組合も月3,500円程度のベースアップを要求するところが多いようだ。
会計事務所を経営し、多くの中小企業を顧客とする身にあって、大企業や大企業の正社員は恵まれていると感じることが少なくない。未だに多くの中小企業では、業績回復には程遠く、ベースアップどころではないというのが多くの中小企業経営者の本音ではないだろうか? また、現在、就労者の相当部分を占める非正規社員(派遣社員、契約社員、パート、アルバイトなど)は、人手不足感のある一部地域、一部業界を除けば、総じて賃金は抑えられたままである。人口が減少し、高齢化がますます進む日本社会では、今後ともこの傾向は続くのではないかとさえ思えるほど、多くの企業は業績低迷に苦しんでいる。2月22日の日経新聞朝刊にも、「休廃業最多3万社、後継者難、高齢化進む」と掲載されていた。なぜ、こうなるのか、答えは簡単。後継者がいないのではなく、事業を引き継ぐほどの魅力がないから、儲からないから引き継いでもしょうがないと周りの人(息子、親戚、従業員など)が思って事業を承継しないからである。
大企業と中小企業、大企業のサラリーマンと中小企業のサラリーマン、大都市と地方都市、富裕層と貧困層、あらゆる分野で格差は拡大している。これは、日本に限ったことではなく、先進国全体の難問でもあるようだ。