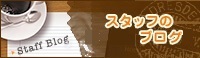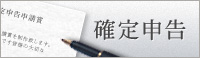今回は、この合同会社の相続に係る注意点をお伝えします。
株式会社の場合、株式を所有している人に相続が発生した場合、当株式は相続財産となり相続人は当然に株式を承継します。
合同会社の場合、出資持分を有している人(=社員と呼びます)に相続が発生した場合には、法定退社事由に該当し退社することとなります。したがって、相続人が社員になることはできません。社員が1名の合同会社の場合、死亡退社により社員がいなくなるため、合同会社は解散することとなります。
その場合でも当然に、合同会社の財産を受け取ることはできますが、相続後も法人として運営していく予定であった場合には、叶わないこととなります。
これを防ぐためには、定款に「社員が死亡した場合、相続人がその社員の持分を承継する旨」を定める必要があります。
これにより、相続により相続人が、社員としての身分をそのまま承継することができます。
また、相続税の評価でも大きな違いが生じることとなります。
A 定款に持分承継できる旨の記載がない場合→相続人が承継する財産は「合同会社に対する出資の
払戻請求権」となり、資産(相続税評価額)ー負債(相続税評価額)で計算された数値に出資持分の割合
を乗じた金額が評価額となります。
B 定款に持分承継できる旨の記載がある場合→相続人が承継する財産は「合同会社に対する出資持分」
となり、非上場株式の相続税評価に準じた方法により評価を行うこととなります。
AとBを比較した場合、次の理由によりBの方が評価額が小さくなる(=相続税が安くなる)ケースが多いと考えられます。
・Bの場合、評価額に類似業種比準価額を加味できる可能性があること。
・Aの場合、Bで行う純資産評価額で控除することができる相続税評価に係る評価益に対する法人税相当
額を控除できないこと。
定款の記載により取り扱いが全く変わることとなりますので、合同会社を経営されている方は、自社の定款をご確認いただくことをおすすめ致します。
合同会社/社員の相続/相続税/出資持分/
山下
- Posted by 2025年03月28日 (金) |
 コメント(0)
コメント(0)
この記事へのコメント
 コメント投稿
コメント投稿
※コメントは承認制のため、投稿をしてもすぐには反映されない場合があります。ご了承ください。
※スパム対策の為、お名前・コメントは必ず入力して下さい。
※記事が削除された場合は、投稿したコメントも削除されます。ご了承ください。