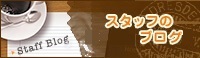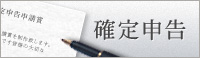上場企業の株式は証券取引所で日々取引されており、誰が売っても買っても同じ価格で取引されます。これを「一物一価(いちぶついっか)」といいます。
ところが、非上場企業(上場していない会社)の株式には市場価格がなく、評価方法や立場によって値段が大きく変わってしまいます。ここが「取引相場のない株式は難しい」と言われる大きな理由です。
例えば、ある会社の株式を相続することになったとしましょう。相続税では国税庁が定めたルール(財産評価基本通達)に従って評価します。あくまで「課税のための評価額」です。
一方、M&Aでその会社を他社が買収する場合は「将来どれだけ利益を生み出せるか」という観点で値段が決まります。その結果、相続税評価では1株あたり1万円と算定された株式が、M&Aでは将来性を高く評価されて1株あたり3万円で取引される、ということも珍しくありません。
さらに、同じ会社の株式でも「誰が持つか」によっても評価額が変わります。
少数株主or支配株主、法人or個人
これらの違いによっても、答えに違いが出てきます。
取引相場のない株式の評価にあたっては、「値段は一つに決まらない」という前提を理解したうえで、誰が取得・保有する株式を評価するのか、求められる評価方法は何かを、慎重に判断し計算することが必要となります。
水野隆啓
- Posted by 2025年08月29日 (金) |
 コメント(0)
コメント(0)
この記事へのコメント
 コメント投稿
コメント投稿
※コメントは承認制のため、投稿をしてもすぐには反映されない場合があります。ご了承ください。
※スパム対策の為、お名前・コメントは必ず入力して下さい。
※記事が削除された場合は、投稿したコメントも削除されます。ご了承ください。