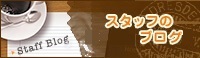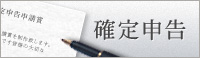実際には、申告書の作成は税理士事務所が行うことがほとんどであることと思いますので、
どのような流れで税額が計算されるのかイメージをつかんでいただける程度に解説いたします。
A.課税価格の算定を行う
被相続人が所有していた財産について評価を行い課税価格を算定する。
B.課税価格より基礎控除額を控除する
基礎控除額は3,000万円+600万円×法定相続人の数です。
Aが基礎控除額(最低3,600万円)を下回る場合、課税価格が0円となるため申告不要です。
C. Bの金額を法定相続分で分割したと仮定する
D. Cの金額について法定相続人ごとに税額表に当てはめ各人の税額を算定する。
E. Dの金額を合計し相続税の総額を算出する。
F. 相続税の総額について、実際の相続人ごとの相続割合で按分する。
Eで計算した相続税の総額のうち、実際に相続した財産の割合分の金額が各相続人の納税額になります
G. 税額控除(加算)を行う
各相続人の実態に合わせた控除(加算)を行い各相続人の納税額を算定する。
詳細は省略しておりますが、おおまかに上記の流れで税額の計算は行われております。
そのため、同じ1億円相当の相続が発生した場合でも、相続人の人数・被相続人との関係などの条件に
よって全く違った税額となります。
山下
- Posted by 2022年08月25日 (木) |
 コメント(0)
コメント(0)
この記事へのコメント
 コメント投稿
コメント投稿
※コメントは承認制のため、投稿をしてもすぐには反映されない場合があります。ご了承ください。
※スパム対策の為、お名前・コメントは必ず入力して下さい。
※記事が削除された場合は、投稿したコメントも削除されます。ご了承ください。