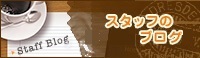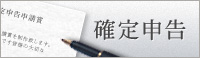原価計算の目的は、「原価計算基準」には以下の5つが示されています。簡単ではありますが、解説してみようと思います。
1.財務諸表作成目的
貸借対照表に記載される製品・仕掛品といった勘定の金額を把握するためのものと考えられるのが一般的かもしれませんが、それよりも適切な期間損益計算のために実施されると考える必要があります。正確な月次利益を把握するためには、決算時だけでなく月次での棚卸が必要不可欠です。
2.価格計算目的
原価がどれだけかかってることを把握したうえで、原価を回収するためにはいくらで販売するかを決めるために必要だという考えです。一般的に、100円の原価のものを90円では販売しません。
3.原価管理目的
現状を把握し、コストダウンにつなげるという目的です。コスト削減するにはまずどれだけのコストがかかっているかを知る必要がありますよね。
4.予算管理目的
予算を立て、その後予実分析をするうえで原価計算をする必要があります。その後、差異分析をし、予算統制手続をすることによりさらなる効果が望めます。
5.経営意思決定目的
上記4つを踏まえ、今後の経営に生かしていく(意思決定に関して有用な資料を提供する)ことを言っています。会社は意思決定の集合体だと言います。正確な原価計算をツールに、より収益性の高い会社を作ろうということです。
読んでみると当たり前のことだと感じるかもれませんが、正確な原価計算が会社をより良い方向に導いてくれる。このことを経営者、経理担当者、そして現場担当者全員が理解する必要があります。会社に合った原価計算はできていますか?
監査課 水野隆啓
浜松/会計事務所/税理士/原価計算/経営
- Posted by 2012年10月03日 (水) |
 コメント(0)
コメント(0)
この記事へのコメント
 コメント投稿
コメント投稿
※コメントは承認制のため、投稿をしてもすぐには反映されない場合があります。ご了承ください。
※スパム対策の為、お名前・コメントは必ず入力して下さい。
※記事が削除された場合は、投稿したコメントも削除されます。ご了承ください。