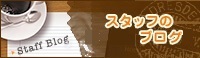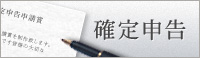(例)①労働者が自ら5日取得した場合⇒使用者の時季指定は不要 ②労働者が自ら3日取得+計画的付与2日の場合⇒使用者の時季指定は不要 ③労働者が自ら3日取得した場合⇒使用者は2日を時季指定する必要がある ④計画的付与で2日取得した場合⇒使用者は3日を時季指定する必要がある
年次有給休暇の時季指定義務がスタートすることで、今後以下について整備する必要があります。
①年次有給休暇の付与ルールの確認⇒年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に5日、指定する必要があるため、就業規則等自社のルールを再度確認する必要がある ②年次有給休暇管理簿の作成が必要 ③年次有給休暇を取得しやすいように業務内容を見直す、あるいは計画的付与を導入するなどを検討
働き方改革の一貫として年次有給休暇の取得率向上に向け舵がきられました。早めの対応を検討しましょう。
会計/税務/法人税/相続税/労務
監査課 平田 晴久
- Posted by 2018年12月24日 (月) |
 コメント(0)
コメント(0)
この記事へのコメント
 コメント投稿
コメント投稿
※コメントは承認制のため、投稿をしてもすぐには反映されない場合があります。ご了承ください。
※スパム対策の為、お名前・コメントは必ず入力して下さい。
※記事が削除された場合は、投稿したコメントも削除されます。ご了承ください。