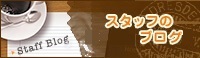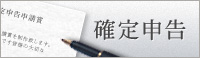相続税の申告書を作成していると、被相続人(故人)が亡くなる少し前に、預貯金口座から現金の引出しが行われているのを頻繁に目にします。これは、金融機関が口座名義人の死亡を把握すると銀行口座が凍結され、遺産分割協議が成立するまでは法定相続人であっても自由な引出しができなくなるため、葬儀代等を工面することを目的に行われているようです。
2019年7月から、被相続人の預貯金を一定額(相続人1人あたり「預貯金額×1/3×法定相続分」、金融機関ごとに150万円を上限)までは引出すことが可能になります。法定相続人であることを証明する書類の提示は必要になろうかと思いますが、相続人にとっては有益な民法改正であることには間違いなさそうです。
水野隆啓
<参考条文>
(遺産の分割前における預貯金債権の行使)
改正民法第909条の2
各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の三分の一に第九百条及び第九百一条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。
浜松市/会計事務所/税理士/公認会計士/相続税
- Posted by 2019年05月31日 (金) |
 コメント(0)
コメント(0)
この記事へのコメント
 コメント投稿
コメント投稿
※コメントは承認制のため、投稿をしてもすぐには反映されない場合があります。ご了承ください。
※スパム対策の為、お名前・コメントは必ず入力して下さい。
※記事が削除された場合は、投稿したコメントも削除されます。ご了承ください。