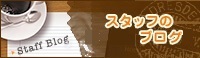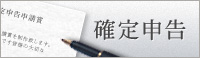相続税の計算は、被相続人から取得した相続財産全体の価額等に基づき計算された相続税額を、財産の取得割合で按分し、各相続人ごとの相続税額を算出します。
その後、各相続人の性格に応じた税額加算・控除(未成年者控除・障害者控除など)が行われ最終的な納付税額が確定することとなります。
相続税の計算において、上記に記載する税額加算は「相続税額の2割加算」1種類のみとなります。
相続税額の2割加算とは、相続により財産を取得したものが配偶者及び一親等の血族(実親・子)以外の者である場合は、計算された相続税額の2/10の金額を納付税額に加算する制度となります。
兄弟姉妹や孫・事実婚関係にあるパートナー等が財産を取得するケースがこれに該当します。
加算を防ぐ方法は1つであり、被相続人の配偶者若しくは一親等の血族になる方法のみとなります。
具体的には、事実婚から法律婚への変更・兄弟姉妹や甥姪を養子にする等となります。
ただし、代襲相続人でない孫を養子にした場合に限っては、当該孫は一親等の血族ではありますが2割加算の対象となります。
また、養子にすることで(相続順位が変動し)法定相続人が減少・税額が増える場合や双方の同意がなければ養子縁組を解除できないため、関係が崩れた場合に相続トラブルに繋がる可能性があるので慎重な検討が必要となります。
相続税に限らず配偶者には様々な税制上のメリットがありますが、法律婚による配偶者を前提として規定されているものがほとんどです。
今後の改正により、事実婚関係にあるパートナーにも適用が広がる可能性はありますが、現時点では事実婚を選択するうえでの大きなデメリットとなっています。
相続税/2割加算/配偶者/事実婚
山下
- Posted by 2025年07月30日 (水) |
 コメント(0)
コメント(0)
この記事へのコメント
 コメント投稿
コメント投稿
※コメントは承認制のため、投稿をしてもすぐには反映されない場合があります。ご了承ください。
※スパム対策の為、お名前・コメントは必ず入力して下さい。
※記事が削除された場合は、投稿したコメントも削除されます。ご了承ください。