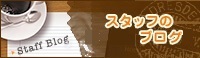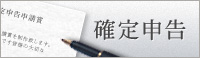平成30年度の税制改正で一般社団法人に対する課税が強化される。一般社団法人には資本金という概念がないため、一般社団法人に個人が所有する不動産・株式等の財産を寄付・譲渡した場合には相続税の対象外となり、相続税対策として広く使われてきた。節税ビジネスを行う税理士やファイナンシャル・プランナー等の開催するセミナー等により広く認知されるようになり、資産家の間で浸透してきたものと思われる。
今回の改正により、同族関係者が理事の過半数を占めている「特定一般社団法人」については、その同族理事の1人が死亡した場合、この一般社団法人に相続税が課税されることとなった。過去に設立された一般社団法人については3年間の経過措置もあるが、すでに実行しているときは、何らかの対応策を詰めておく必要がある。外部から理事を選任して同族関係者の理事の割合を2分の1以下にすれば相続税の課税対象にはならないが、外部の人材を増やせば支配力は弱まり、最悪の場合その一般社団法人を乗っ取られる恐れもないわけではない。
上場企業でも創業者一族等の支配する一般社団法人に株式を割り当てて相続税対策として実行している会社もある。これらの節税策は、あまりに虫が良すぎると警鐘を鳴らしていた専門家も少なくない。今回の税制改正は予想通りであり、節税対策を実行する際には、客観的な判断ができる専門家の意見に耳を傾けるのが賢明である。
2018年03月27日
安易な節税対策は注意!
「税逃れ」対策で税制改正